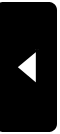2009年05月17日
小石原で呑む
福岡県朝倉郡東峰村の民陶 「小石原焼」

小石原焼は、飛鉋、刷毛目、櫛目、指猫、流し掛け、打掛けなど、
独特の技法が施されている私の好きな陶器の一つ。
もともと10窯だった小石原窯は、日本の陶芸界に大きな影響を与えたことで、
弟子や若手作家の流入により、現在では56もの窯元があります。
昔は「登り窯」で焼成されていたようですが、
現在の小石原の主流は「ガス窯」。
登り窯というのは、山の斜面にそって階段状に焼成室を並べた連房窯。
連続的に焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの作品を一度に焼くことができます。
それぞれの窯にはそれぞれの癖があり、焚き方は窯元の経験と勘だけが頼り。
窯の温度が上がると窯変(ようへん:釉薬成分や炎の性質で偶然起こる素地や釉薬の変化)で、
素晴らしい傑作が生まれることもありますが、温度が高くなり過ぎると釉薬が流れたり、
作品にひびが入ったりします。
窯元が一番神経をすり減らすのがこの時。
なので、窯詰めが終わると、窯上部につまみ塩を置き御神酒を供えて祈願し、火口窯に火を入れます。
逆に言えば、一定量の作品ができてからしか火を入れないので、作品の回転が遅いんです。
時代の変化もあって、温度に均一性があり、小スケールでも焼成できる便利さから、
現在の小石原ではガス窯が主流になったんですね。
ガス窯で焼いた陶器は、艶があり、綺麗に仕上がります。
登り窯とガス窯の仕上がりは異なりますが、そこは「好み」です。
小石原焼とよく似たものに、「小鹿田(おんた)焼」があります。
福岡との県境、大分県日田市で創られる民陶。
技法は小石原から伝わったものであり、姉妹関係にあります。
小鹿焼の原土(陶土)は、他の地域の原土を混ぜない単一の原土で、
すべて集落周辺の山からの自給。採土作業は年2~3回共同で行われ、
掘り山した原士は各窯元で均等に分け、土小屋で乾燥されます。
原土の質は、鉄分や不純物の多い赤い軟岩で、小石原焼と比べると耐火温度において劣ります。
ですが、使いこむと色合いが増してくる味のある土です。
小鹿焼は、今でも昔ながらの「登り窯」で焼成されています。
皿山には、10軒の窯元があり、5軒が共同窯、残りの 5軒が個人窯。
伝統を重んじているのか、小石原のように、窯元を増やさないのだそうです。
そんな薀蓄はさておき、
ゴールデンウィークに福岡に帰省した際に、新たな器を仕入れてきました。
お気に入りの器にご馳走を盛り付けて、美味しいお酒。
いいですよぇ~。

【自家製前菜3種】 【和え物】
・はりはり漬 ・ほうれん草の胡麻和え
・イカめんたい
・島らっきょのおかかまみれ
【好物】 【焼き物】
・じゃこのせ冷奴 ・そら豆の丸焼き
・自家製ぬかづけ
【お飲み物】
・吉兆宝山ロック
今夜は小石原でいっぱい 一杯呑んで、明日からの仕事に備えよ~

小石原焼は、飛鉋、刷毛目、櫛目、指猫、流し掛け、打掛けなど、
独特の技法が施されている私の好きな陶器の一つ。
もともと10窯だった小石原窯は、日本の陶芸界に大きな影響を与えたことで、
弟子や若手作家の流入により、現在では56もの窯元があります。
昔は「登り窯」で焼成されていたようですが、

現在の小石原の主流は「ガス窯」。
登り窯というのは、山の斜面にそって階段状に焼成室を並べた連房窯。
連続的に焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの作品を一度に焼くことができます。
それぞれの窯にはそれぞれの癖があり、焚き方は窯元の経験と勘だけが頼り。
窯の温度が上がると窯変(ようへん:釉薬成分や炎の性質で偶然起こる素地や釉薬の変化)で、
素晴らしい傑作が生まれることもありますが、温度が高くなり過ぎると釉薬が流れたり、
作品にひびが入ったりします。
窯元が一番神経をすり減らすのがこの時。
なので、窯詰めが終わると、窯上部につまみ塩を置き御神酒を供えて祈願し、火口窯に火を入れます。

逆に言えば、一定量の作品ができてからしか火を入れないので、作品の回転が遅いんです。
時代の変化もあって、温度に均一性があり、小スケールでも焼成できる便利さから、
現在の小石原ではガス窯が主流になったんですね。
ガス窯で焼いた陶器は、艶があり、綺麗に仕上がります。
登り窯とガス窯の仕上がりは異なりますが、そこは「好み」です。
小石原焼とよく似たものに、「小鹿田(おんた)焼」があります。

福岡との県境、大分県日田市で創られる民陶。
技法は小石原から伝わったものであり、姉妹関係にあります。
小鹿焼の原土(陶土)は、他の地域の原土を混ぜない単一の原土で、
すべて集落周辺の山からの自給。採土作業は年2~3回共同で行われ、
掘り山した原士は各窯元で均等に分け、土小屋で乾燥されます。
原土の質は、鉄分や不純物の多い赤い軟岩で、小石原焼と比べると耐火温度において劣ります。
ですが、使いこむと色合いが増してくる味のある土です。
小鹿焼は、今でも昔ながらの「登り窯」で焼成されています。
皿山には、10軒の窯元があり、5軒が共同窯、残りの 5軒が個人窯。
伝統を重んじているのか、小石原のように、窯元を増やさないのだそうです。
そんな薀蓄はさておき、
ゴールデンウィークに福岡に帰省した際に、新たな器を仕入れてきました。
お気に入りの器にご馳走を盛り付けて、美味しいお酒。
いいですよぇ~。

【自家製前菜3種】 【和え物】
・はりはり漬 ・ほうれん草の胡麻和え
・イカめんたい
・島らっきょのおかかまみれ
【好物】 【焼き物】
・じゃこのせ冷奴 ・そら豆の丸焼き
・自家製ぬかづけ
【お飲み物】
・吉兆宝山ロック
今夜は小石原で

2009年05月08日
ゴーヤの日
今日は5月8日、ゴーヤの日。
へ?なんで5月8日がゴーヤの日かって?
それは、「5月をさかいにゴーヤーの生産量が増える」ことが大きな理由のようです。
あとは、5月8日は「5・8=ゴーヤー」として語呂がよい、というJA沖縄の策略。
と、言うことで、今年初物のゴーヤちゃんを食べることにしました。

ゴーヤちゃんは、どう料理しても美味しいのですが、
いちばんポピュラーなのが、「ゴーヤチャンプルー」。
チャンプルーというのは、沖縄の方言で「混ぜこぜにした」という意味。
野菜や豆腐に限らず、様々な材料を一緒にした、いわゆる「ナンデモ混ぜこぜ炒め」。
ゴーヤはビタミンCを多く含んでいるだけでなく、
モモルデシンという苦味成分が食欲を増進してくれます。
苦いモノが大好きなyo!としては、
ゴーヤが市場に出回るこれからの季節が、楽しみでなりません。
初物の「ゴーヤちゃん」なので、
とりあえず、「ゴーヤたっぷりチャンプルー」を作ってみました。

【yo!特製 ゴーヤチャンプルーの作り方】
①ゴーヤを縦に2つ割りにして、スプーンでわたを取り除き、うす切りにする。
②その他、入れたい具を用意する。
豚バラ肉、春キャベツ、今回は、冷凍庫で発掘した豚の耳も投入。
③フライパンに油をしき、肉系→ゴーヤ→その他の順に強火で炒める。
④塩コショウ少々、中華ダシ少々、醤油1ちゃぽを加え、少し炒めてできあがり。
※苦いのが苦手な人は、ゴーヤを塩もみして30分位おいておくと、苦味が抜けます。
暑くなると、食欲が落ちてしまう~という方は、
ゴーヤちゃんを食べて、食欲増進させてみては?

へ?なんで5月8日がゴーヤの日かって?
それは、「5月をさかいにゴーヤーの生産量が増える」ことが大きな理由のようです。
あとは、5月8日は「5・8=ゴーヤー」として語呂がよい、というJA沖縄の策略。
と、言うことで、今年初物のゴーヤちゃんを食べることにしました。
ゴーヤちゃんは、どう料理しても美味しいのですが、
いちばんポピュラーなのが、「ゴーヤチャンプルー」。

チャンプルーというのは、沖縄の方言で「混ぜこぜにした」という意味。
野菜や豆腐に限らず、様々な材料を一緒にした、いわゆる「ナンデモ混ぜこぜ炒め」。
ゴーヤはビタミンCを多く含んでいるだけでなく、
モモルデシンという苦味成分が食欲を増進してくれます。
苦いモノが大好きなyo!としては、
ゴーヤが市場に出回るこれからの季節が、楽しみでなりません。
初物の「ゴーヤちゃん」なので、
とりあえず、「ゴーヤたっぷりチャンプルー」を作ってみました。
【yo!特製 ゴーヤチャンプルーの作り方】

①ゴーヤを縦に2つ割りにして、スプーンでわたを取り除き、うす切りにする。
②その他、入れたい具を用意する。
豚バラ肉、春キャベツ、今回は、冷凍庫で発掘した豚の耳も投入。
③フライパンに油をしき、肉系→ゴーヤ→その他の順に強火で炒める。
④塩コショウ少々、中華ダシ少々、醤油1ちゃぽを加え、少し炒めてできあがり。
※苦いのが苦手な人は、ゴーヤを塩もみして30分位おいておくと、苦味が抜けます。
暑くなると、食欲が落ちてしまう~という方は、

ゴーヤちゃんを食べて、食欲増進させてみては?
2009年03月01日
晩酌レシピと七味ごま
花粉症の私にとって、憂鬱なこの時期。
最近の愉しみは、「美味しいもんば食べる」コト。
陽の当たる窓際で、バイブルの「晩酌レシピ」を眺めながら、
今日は何を食べようか・・・?
と、想いを巡らせます。

辛いもの好きの私にとって、七味唐辛子は大好きな調味料の一つ。
焼き鳥、お蕎麦、鍋料理など、
ひと振りするだけで、ピリッと味が引きしまる、魔法の調味料。
日本に七味唐辛子の老舗は三軒あります。
東京・浅草「やげん堀・中島商店」 :生唐辛子、焼き唐辛子の辛さと胡麻の風味が特徴
京都・清水の「七味家本舗」 :山椒・ごま・青のり・紫蘇などの香りが特徴
長野市・善光寺の「八幡屋礒五郎」:バランスのとれた辛味と香りが特徴
今回は、パッケージデザインが可愛らしい、「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子をご紹介します。




七味唐辛子を構成する素材には定義がありません。
「七つの素材=七味」がブレンドされた唐辛子であれば、すべて七味唐辛子なんです。
お店ごとにそれぞれの「七味」があり、その調合に工夫があり、
それが味や香り、色などの特徴となって表れています。
八幡屋礒五郎の七味は、辛味を出すための唐辛子、辛味と香り両方を併せ持つ山椒・生姜、
風味と香りの良い麻の実(麻種)・胡麻・陳皮・紫蘇の七つ。
辛味と香りの調和がとれた独特の味わいが特徴です。



中でもオススメなのが「七味ごま」。
軽く塩コショウした手羽先をグリルで焼いて、「七味ごま」をかけるだけで、プロの味。
スパイシーな唐辛子と芳醇なゴマの香りで、お酒が進みます。っちゅーか止まらなくなります。
そして、焼き鳥の友といえばコレです。
そー言えば、明日の飲み会は焼き鳥だっけ。
「My七味」持って行って、盛り上げちゃお~。
最近の愉しみは、「美味しいもんば食べる」コト。

陽の当たる窓際で、バイブルの「晩酌レシピ」を眺めながら、
今日は何を食べようか・・・?
と、想いを巡らせます。
辛いもの好きの私にとって、七味唐辛子は大好きな調味料の一つ。

焼き鳥、お蕎麦、鍋料理など、
ひと振りするだけで、ピリッと味が引きしまる、魔法の調味料。
日本に七味唐辛子の老舗は三軒あります。
東京・浅草「やげん堀・中島商店」 :生唐辛子、焼き唐辛子の辛さと胡麻の風味が特徴
京都・清水の「七味家本舗」 :山椒・ごま・青のり・紫蘇などの香りが特徴
長野市・善光寺の「八幡屋礒五郎」:バランスのとれた辛味と香りが特徴
今回は、パッケージデザインが可愛らしい、「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子をご紹介します。




七味唐辛子を構成する素材には定義がありません。
「七つの素材=七味」がブレンドされた唐辛子であれば、すべて七味唐辛子なんです。
お店ごとにそれぞれの「七味」があり、その調合に工夫があり、
それが味や香り、色などの特徴となって表れています。
八幡屋礒五郎の七味は、辛味を出すための唐辛子、辛味と香り両方を併せ持つ山椒・生姜、
風味と香りの良い麻の実(麻種)・胡麻・陳皮・紫蘇の七つ。
辛味と香りの調和がとれた独特の味わいが特徴です。



中でもオススメなのが「七味ごま」。

軽く塩コショウした手羽先をグリルで焼いて、「七味ごま」をかけるだけで、プロの味。
スパイシーな唐辛子と芳醇なゴマの香りで、お酒が進みます。っちゅーか止まらなくなります。
そして、焼き鳥の友といえばコレです。
そー言えば、明日の飲み会は焼き鳥だっけ。
「My七味」持って行って、盛り上げちゃお~。

2009年01月31日
必殺料理人
サッパリ釣りに行かなくなった今日この頃。
先日、ブログをいつも見ていただいている方に
「多趣味なyo!君は、最近何してんの?」
と聞かれました。
何してるんだろ?
釣りには行ってないけれど、いろいろと活動はしているんですが・・・。
と考えた結果、
「最近は、料理しとります」
とお答えしました。
昔から料理が好きで、大学時代はアルバイトですが、板前(もどき)をしていたので、
一応、何でも作れるんです。
そこで、今日は今が旬の食材「蕪(かぶ)」を使った料理をご紹介します。
蕪は漬物、煮物と何にしても美味しいですよね。
蕪ちゃんは、春の七草の一つでもあり、最も古い野菜の一つでもあるんです。
古くから土着して多くの地方品種が成立し、日本全国各地に、約80もの品種があります。
蕪の品種は、愛知県と福井県を結ぶラインで作られる品種に違いがあり、
東側は寒さに強い西洋型、一方西側は気温に敏感な日本型の品種が作られています。
この境界線は『かぶライン』と呼ばれています。
そんな余談はさておき、今日は『蕪のコンソメスープ』をご紹介します。
【材料(3~4人分)】
・小かぶ 3個くらい(小さければ多めに)
・豚の挽肉 150g~200g
・しめじ 半株(きのこ大好きなyo!にとっては必須アイテム)
半株(きのこ大好きなyo!にとっては必須アイテム)
・コンソメ 適量
・塩コショウ 少々
・黒胡椒 少々
【作り方】
①油を鍋にしき、豚の挽肉を炒める。
②しめじちゃんを入れ、しんなりする位まで炒める。
③水を入れ、グラっとするまで待つ。
④皮をむいてクシ形切りにした蕪を入れ、蕪の色が半透明になるくらいまで煮る。
⑤下茹でした茎と葉を入れる。(下湯茹でしないとアクがでる)
⑥コンソメ、塩コショウ、黒胡椒を加えてできあがり。
(注1)蕪の茎と葉は美味しいし、栄養がたっぷりなので下茹でしてアク抜きして使う。
(注2)蕪、大根などは火を通してから調味量を入れる。でないと、硬くなって味も染みない。

蕪は火が通りやすいので、火を入れすぎると煮崩れしちゃいます。
サッと火を入れて、とろ~りとした食感をだせるようにしましょう。
スープなのに、焼酎に合うんだなぁ~コレがっ!!
根菜スープを食べて、身体ポカポカ風邪予防。
※具材は上記にこだわらず、好きなものを入れればOK!片栗粉を加えて餡にしてもOKです!
カンタンですので、是非お試しあれ。
先日、ブログをいつも見ていただいている方に
「多趣味なyo!君は、最近何してんの?」
と聞かれました。
何してるんだろ?
釣りには行ってないけれど、いろいろと活動はしているんですが・・・。
と考えた結果、
「最近は、料理しとります」

とお答えしました。
昔から料理が好きで、大学時代はアルバイトですが、板前(もどき)をしていたので、

一応、何でも作れるんです。
そこで、今日は今が旬の食材「蕪(かぶ)」を使った料理をご紹介します。

蕪は漬物、煮物と何にしても美味しいですよね。
蕪ちゃんは、春の七草の一つでもあり、最も古い野菜の一つでもあるんです。
古くから土着して多くの地方品種が成立し、日本全国各地に、約80もの品種があります。
蕪の品種は、愛知県と福井県を結ぶラインで作られる品種に違いがあり、
東側は寒さに強い西洋型、一方西側は気温に敏感な日本型の品種が作られています。
この境界線は『かぶライン』と呼ばれています。

そんな余談はさておき、今日は『蕪のコンソメスープ』をご紹介します。

【材料(3~4人分)】
・小かぶ 3個くらい(小さければ多めに)
・豚の挽肉 150g~200g
・しめじ
 半株(きのこ大好きなyo!にとっては必須アイテム)
半株(きのこ大好きなyo!にとっては必須アイテム)・コンソメ 適量
・塩コショウ 少々
・黒胡椒 少々
【作り方】
①油を鍋にしき、豚の挽肉を炒める。
②しめじちゃんを入れ、しんなりする位まで炒める。
③水を入れ、グラっとするまで待つ。
④皮をむいてクシ形切りにした蕪を入れ、蕪の色が半透明になるくらいまで煮る。
⑤下茹でした茎と葉を入れる。(下湯茹でしないとアクがでる)
⑥コンソメ、塩コショウ、黒胡椒を加えてできあがり。
(注1)蕪の茎と葉は美味しいし、栄養がたっぷりなので下茹でしてアク抜きして使う。
(注2)蕪、大根などは火を通してから調味量を入れる。でないと、硬くなって味も染みない。
蕪は火が通りやすいので、火を入れすぎると煮崩れしちゃいます。
サッと火を入れて、とろ~りとした食感をだせるようにしましょう。
スープなのに、焼酎に合うんだなぁ~コレがっ!!

根菜スープを食べて、身体ポカポカ風邪予防。

※具材は上記にこだわらず、好きなものを入れればOK!片栗粉を加えて餡にしてもOKです!
カンタンですので、是非お試しあれ。

2009年01月18日
一刻者
「一刻者(いっこもん)」とは、南九州で「頑固者」を意味する方言。
そんな名前の芋焼酎があります。
一般の焼酎には、米麹が使われていますが、
「一刻者」は、芋と芋麹だけで仕込んだ『芋100%』の全量芋焼酎。
他にも芋麹使用の芋原料100%焼酎は数銘柄ありますが、
従来の製法で使用されている「蒸し芋」を使った麹は、芋麹をつくるための原料処理方法としては
麹力価(特に、でんぷんの分解力)が米麹に比べて低く、非常に効率の悪い麹となる、という問題点がありました。
麹力価が低いと発酵の進みが悪くなり、香味が単調になったり酸臭が発生し、芋焼酎本来の香りや味が押さえられた焼酎になってしまします。
小牧醸造㈱は、永年の研究により、こうした難点を克服した独自技術の芋麹により、
“芋100%”の特長を十分活かしきった芋焼酎「一刻者」の製品化に成功しました。



(左)一刻者:元祖「一刻者」。芋本来の甘い香りと上品でまろやかな味わいが特徴。
(中)紅一刻:人気の高い芋品種、紅さつまを主原料だけでなく、麹にも使用した
"紅さつま100%"の全量芋焼酎。
(右)黒一刻:芋麹造りにおいて、コクの ある味わいを生む黒麹を用いた
"黒麹仕込"の全量芋焼酎。
そして、今回数量限定で発売されたのが、
金時一刻(きんときいっこ)

あの甘くて美味しい金時芋を主原料だけでなく、麹にも使用した
"金時芋100%"のこだわり全量芋焼酎。
突然ですが、ここでyo!の焼酎の飲み方講座
【ロック】
①ロックグラスに大きめの氷を入れる。
②好みの焼酎を愛情を込めてチョロチョロと注ぎ入れる。
③グラスを回しながら、まずは香りを愉しんで、チビリとお口に流し込む。
④ゆっくりと氷を溶かしながら、味の変化を愉しむ。
【お湯割り】
①冷めにくい酒器にお湯を入れる。(お湯は70~80℃くらいがいい)
②好みの焼酎を焼酎を愛情を込めてチョロチョロと注ぎ入れる。
(注)お湯割りは目にくるので、焼酎:お湯=6:4(ロクヨン)くらいがいいと思う。
【前割り】~意外に知られていない飲み方~
前割りとは、前もって水で割っておいて一晩寝かせておく飲み方。
一晩(以上)寝かせることによって焼酎と水がよく馴染み、よりまろやかな味になるんです。
①好みの焼酎とミネラルウォーター(軟水)を好みの割合で、フタの出来る容器に入れ冷蔵庫に入れる。
②冷蔵庫で一晩以上寝かせ、焼酎と水とを、よくなじませる。
③冷やしたグラスに愛情を込めて注ぎ入れ、目を閉じて口に運ぶ。
毎回こんな面倒くさい飲み方できるかいなっ!?
と、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
いつもと違う飲み方をすることで、
きっと、より美味しく感じられるはずです。
お気に入りの特別な焼酎が手に入った際には、是非お試しあれ。

そんな名前の芋焼酎があります。

一般の焼酎には、米麹が使われていますが、
「一刻者」は、芋と芋麹だけで仕込んだ『芋100%』の全量芋焼酎。
他にも芋麹使用の芋原料100%焼酎は数銘柄ありますが、
従来の製法で使用されている「蒸し芋」を使った麹は、芋麹をつくるための原料処理方法としては
麹力価(特に、でんぷんの分解力)が米麹に比べて低く、非常に効率の悪い麹となる、という問題点がありました。
麹力価が低いと発酵の進みが悪くなり、香味が単調になったり酸臭が発生し、芋焼酎本来の香りや味が押さえられた焼酎になってしまします。
小牧醸造㈱は、永年の研究により、こうした難点を克服した独自技術の芋麹により、
“芋100%”の特長を十分活かしきった芋焼酎「一刻者」の製品化に成功しました。



(左)一刻者:元祖「一刻者」。芋本来の甘い香りと上品でまろやかな味わいが特徴。
(中)紅一刻:人気の高い芋品種、紅さつまを主原料だけでなく、麹にも使用した
"紅さつま100%"の全量芋焼酎。
(右)黒一刻:芋麹造りにおいて、コクの ある味わいを生む黒麹を用いた
"黒麹仕込"の全量芋焼酎。
そして、今回数量限定で発売されたのが、
金時一刻(きんときいっこ)

あの甘くて美味しい金時芋を主原料だけでなく、麹にも使用した
"金時芋100%"のこだわり全量芋焼酎。
突然ですが、ここでyo!の焼酎の飲み方講座

【ロック】
①ロックグラスに大きめの氷を入れる。
②好みの焼酎を愛情を込めてチョロチョロと注ぎ入れる。
③グラスを回しながら、まずは香りを愉しんで、チビリとお口に流し込む。
④ゆっくりと氷を溶かしながら、味の変化を愉しむ。
【お湯割り】
①冷めにくい酒器にお湯を入れる。(お湯は70~80℃くらいがいい)
②好みの焼酎を焼酎を愛情を込めてチョロチョロと注ぎ入れる。
(注)お湯割りは目にくるので、焼酎:お湯=6:4(ロクヨン)くらいがいいと思う。
【前割り】~意外に知られていない飲み方~
前割りとは、前もって水で割っておいて一晩寝かせておく飲み方。
一晩(以上)寝かせることによって焼酎と水がよく馴染み、よりまろやかな味になるんです。
①好みの焼酎とミネラルウォーター(軟水)を好みの割合で、フタの出来る容器に入れ冷蔵庫に入れる。
②冷蔵庫で一晩以上寝かせ、焼酎と水とを、よくなじませる。
③冷やしたグラスに愛情を込めて注ぎ入れ、目を閉じて口に運ぶ。

毎回こんな面倒くさい飲み方できるかいなっ!?
と、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
いつもと違う飲み方をすることで、
きっと、より美味しく感じられるはずです。

お気に入りの特別な焼酎が手に入った際には、是非お試しあれ。

2009年01月18日
桜島溶岩焼き
去年、釣果のタチウオをちょくちょくお裾分けしていた後輩Mちゃん。
年末年始に実家に帰ったからと、こんなお土産を買ってきてくれました。

その名は、
『薩摩の黒酢炊き 桜島溶岩焼
桜島溶岩焼 』
』

これを見るなり、私が発した言葉は、
「これ、タチウオのエサやんっ!!」
私としたことが・・・。
Mちゃんゴメンナサイ。
つい、釣り師の目線で見てしまいました。
それにしても、キビナゴの黒酢煮とは、めちゃお酒が進みそうな・・・。
さすがMちゃん、判ってるねぇ~
【商品説明】
東シナ海とがっぷり向き合った鹿児島県阿久根漁港の前浜で獲れたキビナゴを
一匹ずつ丁寧に炭火で焼き上げ、秘伝のタレでコトコト炊き上げました。
自社農園で生産する黒糖・金ごまと鹿児島県福山町で200年前よりアマン壺と言われる
素焼きの壺に米、米麹、天然水のみを使用した、
伝統的な製法で作られた黒酢をふんだんに使い製造しております。
う~ん、よく判らんケド美味しそうっ!
折角だし、こりゃ限定焼酎と一緒に頂いとかないかんでしょっ!!

ごまと七味をかけて食べたら、激ウマっ!!
一気に食べきっちゃいました。
Mちゃんアリガトー!!
また魚、もって行きマスっ!!
年末年始に実家に帰ったからと、こんなお土産を買ってきてくれました。


その名は、
『薩摩の黒酢炊き
 桜島溶岩焼
桜島溶岩焼 』
』これを見るなり、私が発した言葉は、
「これ、タチウオのエサやんっ!!」
私としたことが・・・。
Mちゃんゴメンナサイ。

つい、釣り師の目線で見てしまいました。
それにしても、キビナゴの黒酢煮とは、めちゃお酒が進みそうな・・・。
さすがMちゃん、判ってるねぇ~

【商品説明】
東シナ海とがっぷり向き合った鹿児島県阿久根漁港の前浜で獲れたキビナゴを
一匹ずつ丁寧に炭火で焼き上げ、秘伝のタレでコトコト炊き上げました。
自社農園で生産する黒糖・金ごまと鹿児島県福山町で200年前よりアマン壺と言われる
素焼きの壺に米、米麹、天然水のみを使用した、
伝統的な製法で作られた黒酢をふんだんに使い製造しております。
う~ん、よく判らんケド美味しそうっ!
折角だし、こりゃ限定焼酎と一緒に頂いとかないかんでしょっ!!

ごまと七味をかけて食べたら、激ウマっ!!

一気に食べきっちゃいました。

Mちゃんアリガトー!!
また魚、もって行きマスっ!!

2009年01月10日
泳げ!たいやき君

年の始めに商売繁盛を祈願するお祭りとして知られている『十日えびす』。
九日 :「宵えびす」
十日 :「本えびす」
十一日:「残り福」
とされ、福の神「えびす様」が奉られている全国の神社で行われています。
「えべっさん」の総本社として知られる兵庫県西宮市の『西宮神社』では十日の早朝、
参拝者が「一番福」を求めて参道を疾走する神事「福男選び」があります。

「福男選び」は江戸時代から続く神事で、上位3人がその年の「福男」に認定されるイベント。
今年の参加者は過去最高の約6000人。
今年も壮絶なデッドヒートの末、3名の「福男」が選ばれたようです。
『西宮神社』のもう一つのイベントは、 「招福巨大マグロ」。


神戸市東部中央卸売場から毎年約300㌔の特大マグロがご神前に奉納されます。
奉納されたマグロは十日えびす三日間に渡ってご神前にお供えされ、
参拝者により硬貨が貼り付けられ、願をかけられるんです。

っていうか、こんなマグロ釣ってみてぇ~




そんなニュースを見ながら、毎年近所の『十日えびす』に参拝しに行くんですが、
そこでいつも買うのがコレ!

シッポの先までアンコたっぷり!
ココのたいやき食べたら、よそのたいやきはもう食べられないほど、美味しいっ!!

たいやきを売っている的屋さんは何軒かあるんですが、毎年買う的屋さんを決めています。

さらに、近所の豆屋さんで美味そうな香りに誘われて、コレも買っちゃいました。

煎りたて甘栗食べて、ほっこり~

今年も良い年になりますように~

2008年12月29日
C'est trés bon
福岡に帰ってきました。
福岡に帰って来たら、必ず行くパン屋さんがあります。
実家のすぐ近くにあって、いつも自転車で立ち寄る『C'est trés bon』

店内で食べることができて、コーヒーも無料。
店員さんに言えば、パンを温めなおしてくれて、焼きたてを満喫できます。
パン好きの私にとっては、たまらないお店。
私好みのハード系のパンが中心で、どれを食べようかと、いつも迷っちゃいます。

C'est trés bonのパンの中で、バゲットなどのハード系は全体の4~5割。
「パンを食事としてとるフランス本場のテイストに近づけたい。
いろいろな素材が入っているものもいいけれど、パンそのものの味を楽しめるパン」というオーナー(大西かおりさん)のこだわりです。
大西さんは、多忙を極める中、時間を作ってはフランスに渡り、
製パン学校の短期コースや現地のパン屋さんでコツコツと修業を積む努力家。
その努力が実り、今ではテレビやラジオで取り上げられる程有名店になりました。
今回セレクトしたのは、
・マカダミアンナッツ&チョコチップのバゲット
・うぐいす豆とひよこ豆のバゲット

この『マカダミアンナッツ&チョコチップのバゲット』がめちゃめちゃ美味いんですよっ!!
このお店に来て、パンを食べると
「あ~、福岡帰ってきたぁ~! 」
」
っていう気分になるんです。
みなさんも、そういうお店ってないですか?

福岡に帰って来たら、必ず行くパン屋さんがあります。
実家のすぐ近くにあって、いつも自転車で立ち寄る『C'est trés bon』

店内で食べることができて、コーヒーも無料。
店員さんに言えば、パンを温めなおしてくれて、焼きたてを満喫できます。
パン好きの私にとっては、たまらないお店。

私好みのハード系のパンが中心で、どれを食べようかと、いつも迷っちゃいます。

C'est trés bonのパンの中で、バゲットなどのハード系は全体の4~5割。
「パンを食事としてとるフランス本場のテイストに近づけたい。
いろいろな素材が入っているものもいいけれど、パンそのものの味を楽しめるパン」というオーナー(大西かおりさん)のこだわりです。
大西さんは、多忙を極める中、時間を作ってはフランスに渡り、
製パン学校の短期コースや現地のパン屋さんでコツコツと修業を積む努力家。
その努力が実り、今ではテレビやラジオで取り上げられる程有名店になりました。
今回セレクトしたのは、
・マカダミアンナッツ&チョコチップのバゲット
・うぐいす豆とひよこ豆のバゲット
この『マカダミアンナッツ&チョコチップのバゲット』がめちゃめちゃ美味いんですよっ!!

このお店に来て、パンを食べると
「あ~、福岡帰ってきたぁ~!
 」
」っていう気分になるんです。
みなさんも、そういうお店ってないですか?

2008年12月25日
Happy Merry Christmas!
今日はChristmas。
いつも良い子にしていたyo!にサンタさんは来るのか?
やっぱり来るのか??
と楽しみにしていたら・・・。
ピンポーン。
「宅急便で~す!」
と、長~い箱を持った配達員。
これはもしや!?
竿?
大きなダンボールからでてきたのは、限定焼酎(爆)。

五代目 和助(本にごり):和助の新酒を無濾過で、うすにごりの状態で瓶詰めした、
年に1度の限定品。白金酒造。
今年は4920本限定発売で、1本1本にシリアルナンバー入り。
宝山:麹にも芋を使い、100%芋(黄金千貫)だけで仕込んだ芋麹全量焼酎。
西酒造から12月17日より発売。
ワインじゃなく、焼酎を飲むクリスマスもいいかも。
サンタさん(親父)、special thanx!!
いつも良い子にしていたyo!にサンタさんは来るのか?

やっぱり来るのか??
と楽しみにしていたら・・・。
ピンポーン。

「宅急便で~す!」

と、長~い箱を持った配達員。
これはもしや!?
竿?
大きなダンボールからでてきたのは、限定焼酎(爆)。

五代目 和助(本にごり):和助の新酒を無濾過で、うすにごりの状態で瓶詰めした、
年に1度の限定品。白金酒造。
今年は4920本限定発売で、1本1本にシリアルナンバー入り。
宝山:麹にも芋を使い、100%芋(黄金千貫)だけで仕込んだ芋麹全量焼酎。
西酒造から12月17日より発売。
ワインじゃなく、焼酎を飲むクリスマスもいいかも。

サンタさん(親父)、special thanx!!

2008年12月21日
とろ~り、とろけちゃうんです
佐賀県、嬉野温泉の名物といえば・・・?
そう、「湯どうふ」です。
嬉野温泉の湯で豆腐を煮込むと煮汁が豆乳色に変わり、
とろ~りとろけちゃうんです!
普通の湯豆腐が煮ると硬くなっていくのに対して、
嬉野温泉の湯どうふは、煮込むほどまろやかになり、
やわらかくとけて白子のような舌触りになります。
これは、嬉野の温泉独特の泉質によるもので、
アルカリ成分が豆腐の植物性蛋白質を分解するため、
煮込むほどにとろけてなめらかな味になり、旨味のある白濁したスープに浸っていくんです。

とろとろ湯どうふに紅葉おろしとカツオ節とポン酢をかけるだけ。
博多っ子の私としては、柚子胡椒なんか入れちゃったりして・・・。
ふわふわ&とろとろ。
こりゃ~美味かばいっ!!!
【嬉野温泉湯とうふ】は和歌山近鉄百貨店でも入手可能!
温泉水とお豆腐のセットでお買い求めください。

そう、「湯どうふ」です。
嬉野温泉の湯で豆腐を煮込むと煮汁が豆乳色に変わり、
とろ~りとろけちゃうんです!
普通の湯豆腐が煮ると硬くなっていくのに対して、
嬉野温泉の湯どうふは、煮込むほどまろやかになり、
やわらかくとけて白子のような舌触りになります。
これは、嬉野の温泉独特の泉質によるもので、
アルカリ成分が豆腐の植物性蛋白質を分解するため、
煮込むほどにとろけてなめらかな味になり、旨味のある白濁したスープに浸っていくんです。
とろとろ湯どうふに紅葉おろしとカツオ節とポン酢をかけるだけ。
博多っ子の私としては、柚子胡椒なんか入れちゃったりして・・・。

ふわふわ&とろとろ。
こりゃ~美味かばいっ!!!

【嬉野温泉湯とうふ】は和歌山近鉄百貨店でも入手可能!
温泉水とお豆腐のセットでお買い求めください。