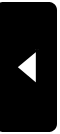2012年03月31日
たけのこまん現る
まさに春に三日の晴れ間なし。
なんなんだ今日の天気は…。
早朝から爆風&豪雨だったのに、昼から晴れてきました。

そんな日の朝、掘りたてのブランド筍をゲット。
和歌山市山東地区は、「たけのこまん」っていう、
ゆるキャラがいるほど筍の産地なんです。

ビミョウなキャラであることは言うまでもありませんが…。
圧力鍋を使えばたった15分で火入れが完了。
あとはじっくり水につけて灰汁をぬくだけ。
旬の筍料理で、今夜は一杯やりますぜよ☆
なんなんだ今日の天気は…。

早朝から爆風&豪雨だったのに、昼から晴れてきました。

そんな日の朝、掘りたてのブランド筍をゲット。
和歌山市山東地区は、「たけのこまん」っていう、
ゆるキャラがいるほど筍の産地なんです。

ビミョウなキャラであることは言うまでもありませんが…。

圧力鍋を使えばたった15分で火入れが完了。
あとはじっくり水につけて灰汁をぬくだけ。
旬の筍料理で、今夜は一杯やりますぜよ☆

2012年03月24日
春告魚
震災の影響で去年は手に入らなかった「いかなご」。
関西では「くぎ煮」にして食される、春を告げる魚です。
今月上旬から市場に出回っていたものの、
週末になると荒天でなかなか出会えずにいましたが、やっと手に入りました。



大阪では今月いっぱいで終漁とのことで、サイズも大きめです。
念願叶って手に入れたいかなご。
気合を入れて、くぎ煮を作ります。
【yo!recipe】
・新鮮な生いかなご 1kg
・濃口醤油 100cc
・たまり醤油 100cc (たまりを加えることでコクがでる)
・酒 150cc
・ざらめ 230g
・みりん 150cc
・土しょうが 100g
・実山椒 好きなだけ
①いかなごをやさしく洗い、ザルにあげてしっかり水を切る
②大きめの鍋に調味料をすべて入れ、強火で煮立たせる
③いかなごを数回に分けて②に投入し、手で調味料と馴染ませる
(手でやさしく馴染ませる・・・魚は冷たいので躊躇わずに手で混ぜる)
④灰汁を丁寧にとる(ここでも強火)
⑤穴を開けたアルミホイルで落し蓋をし、いかなごを煮汁の泡で包み込む
(ふきこぼれない程度の強火で!)
⑥煮汁が見えなくなってきたら中火におとし、さらに数分煮詰める
⑦とろ火に落とし、さらに数分煮詰める(焦がさないように注意する)
⑧煮汁が粘りをもち、鍋を傾けて少なくなったら火を止め、鍋を煽って煮汁を全体に馴染ませる
⑨うちわで扇いで水分を飛ばす(急冷することで照りが増す)
ポイント1:新鮮ないかなごを仕入れること!
鮮度が悪い個体を煮ると、腹が割れ、形がくずれてボロボロになります。
ポイント2:煮ている途中に絶対にかき混ぜないこと!
箸で触ると、形が崩れてボロボロになります。
しょうがたっぷり、実山椒まで入れて、イイ感じに仕上がりました。


こりゃ~しばらくは『春の肴』で呑めますわ
関西では「くぎ煮」にして食される、春を告げる魚です。
今月上旬から市場に出回っていたものの、
週末になると荒天でなかなか出会えずにいましたが、やっと手に入りました。



大阪では今月いっぱいで終漁とのことで、サイズも大きめです。
念願叶って手に入れたいかなご。
気合を入れて、くぎ煮を作ります。

【yo!recipe】
・新鮮な生いかなご 1kg
・濃口醤油 100cc
・たまり醤油 100cc (たまりを加えることでコクがでる)
・酒 150cc
・ざらめ 230g
・みりん 150cc
・土しょうが 100g
・実山椒 好きなだけ
①いかなごをやさしく洗い、ザルにあげてしっかり水を切る
②大きめの鍋に調味料をすべて入れ、強火で煮立たせる
③いかなごを数回に分けて②に投入し、手で調味料と馴染ませる
(手でやさしく馴染ませる・・・魚は冷たいので躊躇わずに手で混ぜる)
④灰汁を丁寧にとる(ここでも強火)
⑤穴を開けたアルミホイルで落し蓋をし、いかなごを煮汁の泡で包み込む
(ふきこぼれない程度の強火で!)
⑥煮汁が見えなくなってきたら中火におとし、さらに数分煮詰める
⑦とろ火に落とし、さらに数分煮詰める(焦がさないように注意する)
⑧煮汁が粘りをもち、鍋を傾けて少なくなったら火を止め、鍋を煽って煮汁を全体に馴染ませる
⑨うちわで扇いで水分を飛ばす(急冷することで照りが増す)
ポイント1:新鮮ないかなごを仕入れること!
鮮度が悪い個体を煮ると、腹が割れ、形がくずれてボロボロになります。
ポイント2:煮ている途中に絶対にかき混ぜないこと!
箸で触ると、形が崩れてボロボロになります。
しょうがたっぷり、実山椒まで入れて、イイ感じに仕上がりました。


こりゃ~しばらくは『春の肴』で呑めますわ

2012年03月11日
蔵開き
自宅から徒歩圏内にある某酒蔵。
今日が蔵開きとあって、はじめて訪れました。

呑み放題もいいとこ、朝から酩酊、極楽ですわ。
コレ全部呑み比べました。

無ろ過非加熱の原酒は芳醇な香りと甘味があるのに対して、
ろ過加熱処理することで、雑味が除かれてスッキリとした飲み口になります。
先週のワインに引き続き、日本酒の奥深さに気づかされました☆
あ~、どうやってウチに帰ってきたのか、覚えとりませんわ…。
今日が蔵開きとあって、はじめて訪れました。

呑み放題もいいとこ、朝から酩酊、極楽ですわ。
コレ全部呑み比べました。
無ろ過非加熱の原酒は芳醇な香りと甘味があるのに対して、
ろ過加熱処理することで、雑味が除かれてスッキリとした飲み口になります。
先週のワインに引き続き、日本酒の奥深さに気づかされました☆
あ~、どうやってウチに帰ってきたのか、覚えとりませんわ…。

2012年03月04日
ワインの目覚め
家の近所のとある酒屋。
今日は「春のワイン試飲会」。
ワインアドバイザーがセレクトした全15種のワインが無料で試飲し放題。
先日たまたま通りがかった洒落た感じの酒屋は、
町家を改装した、檜の香りが漂う正に癒しスポット。
店主からの誘いを受け、朝から夫婦2人で参戦してきました。
朝10時の開店に合わせて訪店すると、すでにワイン好きのお客が顔を赤らめています。
ワインは飲み放題な上、口直しにパンやチーズも食べ放題。
試飲と言っていながらも、店主とお客さんで盛り上がる、いわば飲み会状態。
試飲時間はトータル2時間。
あーだこーだ薀蓄を傾けながら、1本分は飲んだはずです。
満喫しすぎて、お昼ご飯が食べられましぇん。

今回の試飲(呑み放題)ワインは下記の15種。
①クッド・アリアニーコ・ロサート・ブリュットNV
②IGTインツォリア コンテ・ディ・アタロツコ2010
③ブルゴーニュ・アリゴテ2009
④ザ・ラッキー・リースリング2010
⑤シャトー・グラン・ヴィラージュ・ブラン2006
⑥モンタニー1級畑2008
⑦サン・トーヴァン2008
⑧ブルグライヤー・シュロスカペレ・バフースQbA2010
⑨サライカルベネ・フラン2010
⑩レンゼ2010
⑪スペルバウンド2009
⑫ロイ・ルージュ2007
⑬グラン・キュヴェ・ルージュ2007
⑭CHグラン・ヴィラージュ・ルージュ2005
⑮リオハ・ティント・レゼルバ2005
あ、試飲だけぢゃなく、ちゃんとワインも買って帰りましたよ。
今回は妻の誕生日用に⑤をセレクト。
いつもは焼酎ばかりですが、ワインに目覚めた気がします。
ヤバイ…。
今日は「春のワイン試飲会」。

ワインアドバイザーがセレクトした全15種のワインが無料で試飲し放題。

先日たまたま通りがかった洒落た感じの酒屋は、
町家を改装した、檜の香りが漂う正に癒しスポット。
店主からの誘いを受け、朝から夫婦2人で参戦してきました。
朝10時の開店に合わせて訪店すると、すでにワイン好きのお客が顔を赤らめています。
ワインは飲み放題な上、口直しにパンやチーズも食べ放題。
試飲と言っていながらも、店主とお客さんで盛り上がる、いわば飲み会状態。

試飲時間はトータル2時間。
あーだこーだ薀蓄を傾けながら、1本分は飲んだはずです。
満喫しすぎて、お昼ご飯が食べられましぇん。

今回の試飲(呑み放題)ワインは下記の15種。
①クッド・アリアニーコ・ロサート・ブリュットNV
②IGTインツォリア コンテ・ディ・アタロツコ2010
③ブルゴーニュ・アリゴテ2009
④ザ・ラッキー・リースリング2010
⑤シャトー・グラン・ヴィラージュ・ブラン2006
⑥モンタニー1級畑2008
⑦サン・トーヴァン2008
⑧ブルグライヤー・シュロスカペレ・バフースQbA2010
⑨サライカルベネ・フラン2010
⑩レンゼ2010
⑪スペルバウンド2009
⑫ロイ・ルージュ2007
⑬グラン・キュヴェ・ルージュ2007
⑭CHグラン・ヴィラージュ・ルージュ2005
⑮リオハ・ティント・レゼルバ2005
あ、試飲だけぢゃなく、ちゃんとワインも買って帰りましたよ。
今回は妻の誕生日用に⑤をセレクト。
いつもは焼酎ばかりですが、ワインに目覚めた気がします。
ヤバイ…。

2011年11月12日
伊勢海老よりも甘く、車海老よりも柔らかい
漁師も絶賛する紀州自慢のブランド海老。
それは、
「足赤えび」



一般には「クマエビ」と呼ばれているエビで、海外産は多く流通していますが、
国産のクマエビは漁獲量も少なく、殆どは漁獲地で消費されてしまうため、
市場に流通する量はごくわずか。
しかしながら、紀伊水道北部では近年「足赤えび」の漁獲量が急増。


和歌山は全国でもトップクラスの水揚げ量だとか。
yo!の住む紀北では10月中旬から5月にかけて漁が行われ、11月から2月が最も旬。
そんなに美味しい旬の海老があるのなら、食べてみようかと近所の市場へ。
ほ~んと!その名のとおり、赤い足。

海老の一番美味しい食べ方といえば、塩焼き。
Simple is best!
塩気と火を通すことで甘味が増し、食感も良くなります◎

際立つ甘味と柔らかな食感

旬とあってか海老ミソもたっぷりクリーミー。
こげな美味いモンが相手とあっちゃ、失礼があっちゃなんねぇ。
昼間っから飲んぢまっただぁ~

それは、
「足赤えび」



一般には「クマエビ」と呼ばれているエビで、海外産は多く流通していますが、
国産のクマエビは漁獲量も少なく、殆どは漁獲地で消費されてしまうため、
市場に流通する量はごくわずか。
しかしながら、紀伊水道北部では近年「足赤えび」の漁獲量が急増。



和歌山は全国でもトップクラスの水揚げ量だとか。
yo!の住む紀北では10月中旬から5月にかけて漁が行われ、11月から2月が最も旬。
そんなに美味しい旬の海老があるのなら、食べてみようかと近所の市場へ。

ほ~んと!その名のとおり、赤い足。
海老の一番美味しい食べ方といえば、塩焼き。
Simple is best!
塩気と火を通すことで甘味が増し、食感も良くなります◎

際立つ甘味と柔らかな食感


旬とあってか海老ミソもたっぷりクリーミー。

こげな美味いモンが相手とあっちゃ、失礼があっちゃなんねぇ。
昼間っから飲んぢまっただぁ~

2011年11月03日
いもいもトロリ
11月だっていうのに暖かい日が続いています。
例年よりも5℃も高いそうです。
でも市場やスーパーには秋の味覚がズラリ。


気温は高くても自然は季節を感じ取って実をつけるんですね。
なんかね、突然コレが食べたくなったんです。
サトイモとスルメイカの煮物。




yo!が作るスルメイカ料理は、他店では味わえないモノばかり。
なんでかってね、肝を使うんですよ、肝を。
今の時季が旬のスルメイカは肝がパンパン。
この肝を使わない手はない。
芳醇な肝の香り、甘~い芋焼酎にサトイモがトロリ。
思わず目を閉じてしまう、絶品料理です。


是非、お試しあれ。
【サトイモとイカの煮物】
①サトイモを軽く洗って軽く蒸し、手で皮をむく。
②大切な肝を傷つけないようにスルメイカを裁く。
③煮だしに肝を入れて溶かし、火を入れる。
④煮だしがグツグツしてきたらサトイモとスルメイカを入れて一煮立ちさせる。
⑤煮立ったら冷まして味をなじませる(サトイモが煮くずれないよう一煮立ちでOK)。
※サトイモは圧力鍋で1分蒸せば皮がプリっとむけます。
あとはそのまま圧力をかけずに煮ればカンタン。

(煮だし)
・水 適量
・ほんだし 少々
・薄口しょうゆ 少々
・みりん 少々
・酒 好きなだけ

例年よりも5℃も高いそうです。

でも市場やスーパーには秋の味覚がズラリ。



気温は高くても自然は季節を感じ取って実をつけるんですね。
なんかね、突然コレが食べたくなったんです。
サトイモとスルメイカの煮物。



yo!が作るスルメイカ料理は、他店では味わえないモノばかり。
なんでかってね、肝を使うんですよ、肝を。
今の時季が旬のスルメイカは肝がパンパン。
この肝を使わない手はない。
芳醇な肝の香り、甘~い芋焼酎にサトイモがトロリ。
思わず目を閉じてしまう、絶品料理です。



是非、お試しあれ。

【サトイモとイカの煮物】

①サトイモを軽く洗って軽く蒸し、手で皮をむく。
②大切な肝を傷つけないようにスルメイカを裁く。
③煮だしに肝を入れて溶かし、火を入れる。
④煮だしがグツグツしてきたらサトイモとスルメイカを入れて一煮立ちさせる。
⑤煮立ったら冷まして味をなじませる(サトイモが煮くずれないよう一煮立ちでOK)。
※サトイモは圧力鍋で1分蒸せば皮がプリっとむけます。
あとはそのまま圧力をかけずに煮ればカンタン。


(煮だし)
・水 適量
・ほんだし 少々
・薄口しょうゆ 少々
・みりん 少々
・酒 好きなだけ
2011年07月18日
夏といえば…
やっぱりカレー。

毎年この時季に、ロイヤルホストがやっている「夏のカレーフェア」。
そんなカレーフェアも今年でナント29回目。


今回は本物のカレーの美味しさや、カレーが本来もっている“ちから”を実感できるように
『実感“カレーの底ぢから”』をテーマに、バラエティ豊かな本格カレー全6品を展開しています。
ウチはファミレスなんかじゃない、一流のレストランなんだ。


と、誇りをもったシェフが集うロイホ。
そんなシェフ達が、ファミレスと一線を画すために行っているフェアでもあります。
だからロイホのカレーはウマイっ!!!


今年のカレーフェアでyo!が迷わず注文したのは「ロイヤルターリ」。
マレーシアで食べてハマったパロタと3種類のカレーがセットになった贅沢なセット。
辛くて口から火を吹くといけないので、生ビール(大)もご一緒に。


いや~美味しかった。
文句ナシですよ、ホントに。
特にパロタが美味い。本場のパロタそのものでしたよ◎
パロタとは、サクサク、モチモチの食感が人気のインドのクロワッサンと呼ばれるパン。
マレーシアに行った時、これにハマって毎日カレーを食べていました。


その感動を自宅でも味わいたくて、作ってみましたよ、パロタ。
【生地の作り方】
下記材料をホームベーカリーに入れて、生地を作る。これが一番ラクで美味しい。


強力粉 280g バター 15g
砂糖 大1 スキムミルク 大1
塩 小1 ドライイースト 小1
水 180mL
①ピンポン玉位の大きさに生地を丸めて ②バターでギトギトの手のひらで軽く伸ばす


③麺棒で生地をできるだけ薄くのばして ④バターでギトギトの手でクルクルと棒状にする


⑤棒状にした生地を渦巻状に丸めて ⑥端は生地の下に入れてできあがり


あとは手でつぶして平面状にし、サラダ油を塗ったフライパンで両面を焼けばできあがり。



サクサク、モチモチ。カレーにちびちび付けながら食べれば、
ほっぺたが落ちることマチガイナシ。
自家製パロタセット。
マレーシアでは飲めなかったけど、コレがまた焼酎に合うのなんのって・・・。
昼間っから飲んぢまっただぁ~



毎年この時季に、ロイヤルホストがやっている「夏のカレーフェア」。
そんなカレーフェアも今年でナント29回目。



今回は本物のカレーの美味しさや、カレーが本来もっている“ちから”を実感できるように
『実感“カレーの底ぢから”』をテーマに、バラエティ豊かな本格カレー全6品を展開しています。
ウチはファミレスなんかじゃない、一流のレストランなんだ。



と、誇りをもったシェフが集うロイホ。
そんなシェフ達が、ファミレスと一線を画すために行っているフェアでもあります。
だからロイホのカレーはウマイっ!!!



今年のカレーフェアでyo!が迷わず注文したのは「ロイヤルターリ」。

マレーシアで食べてハマったパロタと3種類のカレーがセットになった贅沢なセット。
辛くて口から火を吹くといけないので、生ビール(大)もご一緒に。


いや~美味しかった。

文句ナシですよ、ホントに。
特にパロタが美味い。本場のパロタそのものでしたよ◎
パロタとは、サクサク、モチモチの食感が人気のインドのクロワッサンと呼ばれるパン。
マレーシアに行った時、これにハマって毎日カレーを食べていました。



その感動を自宅でも味わいたくて、作ってみましたよ、パロタ。

【生地の作り方】
下記材料をホームベーカリーに入れて、生地を作る。これが一番ラクで美味しい。



強力粉 280g バター 15g
砂糖 大1 スキムミルク 大1
塩 小1 ドライイースト 小1
水 180mL
①ピンポン玉位の大きさに生地を丸めて ②バターでギトギトの手のひらで軽く伸ばす
③麺棒で生地をできるだけ薄くのばして ④バターでギトギトの手でクルクルと棒状にする
⑤棒状にした生地を渦巻状に丸めて ⑥端は生地の下に入れてできあがり
あとは手でつぶして平面状にし、サラダ油を塗ったフライパンで両面を焼けばできあがり。



サクサク、モチモチ。カレーにちびちび付けながら食べれば、

ほっぺたが落ちることマチガイナシ。
自家製パロタセット。
マレーシアでは飲めなかったけど、コレがまた焼酎に合うのなんのって・・・。
昼間っから飲んぢまっただぁ~


2011年07月17日
桃の争奪戦
7月中旬。
とうとうこの季節がやってきました。



そう、 桃 の季節です。
桃と言っても、そんじょそこらで売っているただの桃じゃありません。
和歌山県紀の川市桃山町で作られた「あら川の桃」。
一般の桃よりも大ぶりで甘いのが特徴のブランド桃なんです。
このブランド桃を激安で買えるとあって、
毎年この時期に行くのが「めっけもん広場」。
よくある産地直売所のファーマーズマーケットなんですが、
なんと売上高は日本一。
年間売り上げが26億円強、年間来訪者が80万人強、納入生産者が1600戸
というとんでもないファーマーズマーケット。
しかも今日は第一回桃の特別販売日とあって、
めっけもん広場の周りは、ありえないくらいの大渋滞。
駐車場にたどり着くのに1時間以上かかることもザラです。
そんな桃渋滞を尻目にyo!はバイクで渋滞フリー


渋滞をすり抜けて、開店1時間後に運よくお店に到着するも、店内は人、人、人…。


桃の売り場にたどり着くのに一苦労。
やっとのことで売り場に到着すると、
「桃、売り切れました~」
「は?」
開店1時間で売り切れって、どういうことやねん。
生産者が持ってきた瞬間に桃の争奪戦が始まり、すぐに売切れてしまう盛況ぶり。
入場制限までかかり、おばちゃん達の列に並んで順番を待ちます。

30分ほど並んで、やっとゲットしましたよ。



なんとも微笑ましい、まぁ~るい形と甘~い香り。

はよ食べたい。



お世話になっている方々へも宅急便でお送りしましたので、是非ご賞味下さいませ。
【桃の正しい食べ方】
①食べる直前まで常温で保存する。
②食べる1時間前に冷蔵庫に入れてやさしく冷やす。
③皮をむいて、むさぼりつく。
(注)冷蔵庫に長時間入れると甘味と風味が飛んじゃいます。

とうとうこの季節がやってきました。

そう、 桃 の季節です。
桃と言っても、そんじょそこらで売っているただの桃じゃありません。
和歌山県紀の川市桃山町で作られた「あら川の桃」。
一般の桃よりも大ぶりで甘いのが特徴のブランド桃なんです。
このブランド桃を激安で買えるとあって、
毎年この時期に行くのが「めっけもん広場」。
よくある産地直売所のファーマーズマーケットなんですが、
なんと売上高は日本一。
年間売り上げが26億円強、年間来訪者が80万人強、納入生産者が1600戸
というとんでもないファーマーズマーケット。
しかも今日は第一回桃の特別販売日とあって、
めっけもん広場の周りは、ありえないくらいの大渋滞。
駐車場にたどり着くのに1時間以上かかることもザラです。
そんな桃渋滞を尻目にyo!はバイクで渋滞フリー



渋滞をすり抜けて、開店1時間後に運よくお店に到着するも、店内は人、人、人…。



桃の売り場にたどり着くのに一苦労。
やっとのことで売り場に到着すると、
「桃、売り切れました~」
「は?」

開店1時間で売り切れって、どういうことやねん。
生産者が持ってきた瞬間に桃の争奪戦が始まり、すぐに売切れてしまう盛況ぶり。
入場制限までかかり、おばちゃん達の列に並んで順番を待ちます。


30分ほど並んで、やっとゲットしましたよ。




なんとも微笑ましい、まぁ~るい形と甘~い香り。

はよ食べたい。




お世話になっている方々へも宅急便でお送りしましたので、是非ご賞味下さいませ。

【桃の正しい食べ方】

①食べる直前まで常温で保存する。
②食べる1時間前に冷蔵庫に入れてやさしく冷やす。
③皮をむいて、むさぼりつく。
(注)冷蔵庫に長時間入れると甘味と風味が飛んじゃいます。
2011年06月05日
梅雨のはしりが過ぎた頃…
やらねばならぬコトがあります。
2年後に開けるタイムカプセル
勘の良い方は、お判りですよね。
そう、
酒の仕込み。
今の季節、地元和歌山のスーパーや道の駅には、梅、梅、梅、と梅が溢れています。
日本一の生産量を誇る和歌山県みなべ町の南高梅が、5月末に発生した台風によって多数落下。
なんとか枝にしがみついて耐えた梅にも、折れた枝で擦り傷のような跡がつき、大幅な出荷減。
と言われている中、地元スーパーには梅がいっぱい。

しかも激安、1㌔298円。


ところで、梅酒づくりに溶けにくい氷砂糖をなぜ使うか知っていますか?
顆粒の砂糖を使えば、あっちゅう間に溶けるのに…。
氷砂糖でなければ駄目な理由があるんですよ、これがまた。
これは、「溶けにくい」という性質を利用して、
梅のエキスや香りを引き出すためなんです。
梅酒づくりのポイントは、2度の浸透圧を利用するということ。
一般的に、梅酒を作る時に使うのは、
青梅、焼酎(ホワイトリカー)、氷砂糖 の3つ。
これを役割分担させてみると、
・エキスや香りの元:梅
・浸透圧を使って梅のエキスを引き出すもの:焼酎と氷砂糖
となります。
梅のエキスや香りなどは、梅の実の中にありますが、
これが出てくるきっかけの第1段階が、アルコール分子と水分(焼酎)。
梅の実の中にある糖分が、実の外と同じ糖度にしようとして、
実の外にあるアルコールと水分子を実の中に引っ張ります。
梅の実から、糖分が外に出れば良いのでは?と思いますが、
梅の表面にあいている小さな穴は、アルコールや水のように
小さい分子を通す事が出来ても、糖分を通す事は出来ません。
そのため、実の外にあるアルコールや水の分子を、実の中に引っ張ります。
その結果、元々の梅の実よりも、膨らみます。


そして、アルコールと仲が良い芳香成分などのエキスが、
梅の実の中に入ってきたアルコールに溶け出します。
これが最初に起こる浸透圧の働き。
※この梅の実が膨らんだ状態は、梅の実が酔っぱらった状態
そして、次にはたらくのが氷砂糖。
氷砂糖は、その特性から、じわじわと焼酎の中に溶けて行きます。
氷砂糖がじわじわ溶ける事で、梅の実の外では少しずつ糖度が上がっていきます。
最初の浸透圧では、梅の実の外よりも梅の実の中の糖度が高いため、
アルコールや水分が梅の実の中に入って行きましたが、今度はその逆が起こります。
梅の実の糖度よりも梅の外の糖度が上回ると、今までの圧力バランスが崩れ、
今度は梅の実の中に入っていたアルコールやエキスなどが外に引っ張り出されます。
その結果、梅がしぼみ始めます。
これが第2段階の浸透圧。
ゆっくりと時間をかけてこの反応を起こすことで、コクのある美味しい梅酒ができるんです。
これらの反応が落ち着くまでには、半年から1年。
糖度が低い場合には、第2段階の浸透圧が低いため、さらに時間がかかります。
甘~いお酒が苦手なyo!が作る梅酒は、糖度が低め。
そのため、梅のエキスがでて、まろやかになるまで2年以上かかります。
だから、いつも多めに(4㍑)作ります。


【yo!特製梅酒の作り方】~甘さひかえめ~
・青梅 1kg
・氷砂糖 330g
・焼酎 2L
①青梅を1時間ほど水にさらして灰汁をぬく。
②青梅のヘタを取ってキレイに洗い、自然乾燥させる。
③②の梅→氷砂糖→梅→氷砂糖→梅→…の順に容器に入れる。
④未練を残さず、豪快に焼酎を注ぎ入れる。
⑤「ちょっと味見…」などとチョッカイを出さず、2年経つまで冷暗所で保存する。
※糖分が均等になるように、時々ビンを揺り動かして「美味しくなぁ~れぇ~」と唱える
スーパーで青梅を見かけたら、みなさんも是非、お試しあれ。
2年後に開けるタイムカプセル

勘の良い方は、お判りですよね。
そう、
酒の仕込み。

今の季節、地元和歌山のスーパーや道の駅には、梅、梅、梅、と梅が溢れています。
日本一の生産量を誇る和歌山県みなべ町の南高梅が、5月末に発生した台風によって多数落下。
なんとか枝にしがみついて耐えた梅にも、折れた枝で擦り傷のような跡がつき、大幅な出荷減。
と言われている中、地元スーパーには梅がいっぱい。

しかも激安、1㌔298円。



ところで、梅酒づくりに溶けにくい氷砂糖をなぜ使うか知っていますか?
顆粒の砂糖を使えば、あっちゅう間に溶けるのに…。
氷砂糖でなければ駄目な理由があるんですよ、これがまた。
これは、「溶けにくい」という性質を利用して、
梅のエキスや香りを引き出すためなんです。
梅酒づくりのポイントは、2度の浸透圧を利用するということ。
一般的に、梅酒を作る時に使うのは、

青梅、焼酎(ホワイトリカー)、氷砂糖 の3つ。
これを役割分担させてみると、
・エキスや香りの元:梅
・浸透圧を使って梅のエキスを引き出すもの:焼酎と氷砂糖
となります。
梅のエキスや香りなどは、梅の実の中にありますが、
これが出てくるきっかけの第1段階が、アルコール分子と水分(焼酎)。
梅の実の中にある糖分が、実の外と同じ糖度にしようとして、
実の外にあるアルコールと水分子を実の中に引っ張ります。
梅の実から、糖分が外に出れば良いのでは?と思いますが、
梅の表面にあいている小さな穴は、アルコールや水のように
小さい分子を通す事が出来ても、糖分を通す事は出来ません。
そのため、実の外にあるアルコールや水の分子を、実の中に引っ張ります。
その結果、元々の梅の実よりも、膨らみます。



そして、アルコールと仲が良い芳香成分などのエキスが、
梅の実の中に入ってきたアルコールに溶け出します。
これが最初に起こる浸透圧の働き。
※この梅の実が膨らんだ状態は、梅の実が酔っぱらった状態

そして、次にはたらくのが氷砂糖。

氷砂糖は、その特性から、じわじわと焼酎の中に溶けて行きます。
氷砂糖がじわじわ溶ける事で、梅の実の外では少しずつ糖度が上がっていきます。
最初の浸透圧では、梅の実の外よりも梅の実の中の糖度が高いため、
アルコールや水分が梅の実の中に入って行きましたが、今度はその逆が起こります。
梅の実の糖度よりも梅の外の糖度が上回ると、今までの圧力バランスが崩れ、
今度は梅の実の中に入っていたアルコールやエキスなどが外に引っ張り出されます。
その結果、梅がしぼみ始めます。

これが第2段階の浸透圧。
ゆっくりと時間をかけてこの反応を起こすことで、コクのある美味しい梅酒ができるんです。
これらの反応が落ち着くまでには、半年から1年。
糖度が低い場合には、第2段階の浸透圧が低いため、さらに時間がかかります。
甘~いお酒が苦手なyo!が作る梅酒は、糖度が低め。
そのため、梅のエキスがでて、まろやかになるまで2年以上かかります。
だから、いつも多めに(4㍑)作ります。


【yo!特製梅酒の作り方】~甘さひかえめ~
・青梅 1kg
・氷砂糖 330g
・焼酎 2L
①青梅を1時間ほど水にさらして灰汁をぬく。
②青梅のヘタを取ってキレイに洗い、自然乾燥させる。
③②の梅→氷砂糖→梅→氷砂糖→梅→…の順に容器に入れる。
④未練を残さず、豪快に焼酎を注ぎ入れる。
⑤「ちょっと味見…」などとチョッカイを出さず、2年経つまで冷暗所で保存する。
※糖分が均等になるように、時々ビンを揺り動かして「美味しくなぁ~れぇ~」と唱える

スーパーで青梅を見かけたら、みなさんも是非、お試しあれ。

2010年09月22日
北海道ぐるり旅 ~番外編~
帰りにホッケの開きでも買って帰ろうと、札幌駅にある大丸の地下に寄りました。
ホッケの開きを買った魚屋のおばちゃんが、
「今が旬のイクラはどう?」
とオススメしてくれたので、ついでにお買い上げ。
そう、秋鮭って今が旬ですよね~。
一昨年の北海道遠征を思い出しますわ。


30~40℃の塩水でバラして、
昆布、醤油、酒、みりんを煮きったあわせだしに一晩漬け込んで、
「美味しくなぁ~れぇ~」と念じるだけ。

赤いダイヤを秋にしか味わえない日本酒「七人の侍 ひやおろし」で流し込みます。



旬の赤いダイヤを旬の酒で流し込む。

これって今の季節にしかできない最高の贅沢です。


日本酒ばんざ~い



【ひやおろし】
冬に搾られたお酒は、殺菌などを目的に加熱処理をされタンクに貯蔵されます。
暑い夏が過ぎ季節が秋を迎えるころ、蔵で静かに貯蔵されたお酒は、
ほどよく熟成し、香り、味ともに飲み頃となります。
通常、お酒は瓶詰めするときに、再度加熱処理をします。
その加熱処理をせず、「冷や」のまま瓶詰めされた生詰めのお酒は、
「ひやおろし」と呼ばれ、秋にしか味わえない美味しいお酒らしいです。
ホッケの開きを買った魚屋のおばちゃんが、

「今が旬のイクラはどう?」
とオススメしてくれたので、ついでにお買い上げ。
そう、秋鮭って今が旬ですよね~。
一昨年の北海道遠征を思い出しますわ。



30~40℃の塩水でバラして、

昆布、醤油、酒、みりんを煮きったあわせだしに一晩漬け込んで、
「美味しくなぁ~れぇ~」と念じるだけ。

赤いダイヤを秋にしか味わえない日本酒「七人の侍 ひやおろし」で流し込みます。



旬の赤いダイヤを旬の酒で流し込む。


これって今の季節にしかできない最高の贅沢です。



日本酒ばんざ~い



【ひやおろし】
冬に搾られたお酒は、殺菌などを目的に加熱処理をされタンクに貯蔵されます。
暑い夏が過ぎ季節が秋を迎えるころ、蔵で静かに貯蔵されたお酒は、
ほどよく熟成し、香り、味ともに飲み頃となります。
通常、お酒は瓶詰めするときに、再度加熱処理をします。
その加熱処理をせず、「冷や」のまま瓶詰めされた生詰めのお酒は、
「ひやおろし」と呼ばれ、秋にしか味わえない美味しいお酒らしいです。