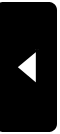2011年06月05日
梅雨のはしりが過ぎた頃…
やらねばならぬコトがあります。
2年後に開けるタイムカプセル
勘の良い方は、お判りですよね。
そう、
酒の仕込み。
今の季節、地元和歌山のスーパーや道の駅には、梅、梅、梅、と梅が溢れています。
日本一の生産量を誇る和歌山県みなべ町の南高梅が、5月末に発生した台風によって多数落下。
なんとか枝にしがみついて耐えた梅にも、折れた枝で擦り傷のような跡がつき、大幅な出荷減。
と言われている中、地元スーパーには梅がいっぱい。

しかも激安、1㌔298円。


ところで、梅酒づくりに溶けにくい氷砂糖をなぜ使うか知っていますか?
顆粒の砂糖を使えば、あっちゅう間に溶けるのに…。
氷砂糖でなければ駄目な理由があるんですよ、これがまた。
これは、「溶けにくい」という性質を利用して、
梅のエキスや香りを引き出すためなんです。
梅酒づくりのポイントは、2度の浸透圧を利用するということ。
一般的に、梅酒を作る時に使うのは、
青梅、焼酎(ホワイトリカー)、氷砂糖 の3つ。
これを役割分担させてみると、
・エキスや香りの元:梅
・浸透圧を使って梅のエキスを引き出すもの:焼酎と氷砂糖
となります。
梅のエキスや香りなどは、梅の実の中にありますが、
これが出てくるきっかけの第1段階が、アルコール分子と水分(焼酎)。
梅の実の中にある糖分が、実の外と同じ糖度にしようとして、
実の外にあるアルコールと水分子を実の中に引っ張ります。
梅の実から、糖分が外に出れば良いのでは?と思いますが、
梅の表面にあいている小さな穴は、アルコールや水のように
小さい分子を通す事が出来ても、糖分を通す事は出来ません。
そのため、実の外にあるアルコールや水の分子を、実の中に引っ張ります。
その結果、元々の梅の実よりも、膨らみます。


そして、アルコールと仲が良い芳香成分などのエキスが、
梅の実の中に入ってきたアルコールに溶け出します。
これが最初に起こる浸透圧の働き。
※この梅の実が膨らんだ状態は、梅の実が酔っぱらった状態
そして、次にはたらくのが氷砂糖。
氷砂糖は、その特性から、じわじわと焼酎の中に溶けて行きます。
氷砂糖がじわじわ溶ける事で、梅の実の外では少しずつ糖度が上がっていきます。
最初の浸透圧では、梅の実の外よりも梅の実の中の糖度が高いため、
アルコールや水分が梅の実の中に入って行きましたが、今度はその逆が起こります。
梅の実の糖度よりも梅の外の糖度が上回ると、今までの圧力バランスが崩れ、
今度は梅の実の中に入っていたアルコールやエキスなどが外に引っ張り出されます。
その結果、梅がしぼみ始めます。
これが第2段階の浸透圧。
ゆっくりと時間をかけてこの反応を起こすことで、コクのある美味しい梅酒ができるんです。
これらの反応が落ち着くまでには、半年から1年。
糖度が低い場合には、第2段階の浸透圧が低いため、さらに時間がかかります。
甘~いお酒が苦手なyo!が作る梅酒は、糖度が低め。
そのため、梅のエキスがでて、まろやかになるまで2年以上かかります。
だから、いつも多めに(4㍑)作ります。


【yo!特製梅酒の作り方】~甘さひかえめ~
・青梅 1kg
・氷砂糖 330g
・焼酎 2L
①青梅を1時間ほど水にさらして灰汁をぬく。
②青梅のヘタを取ってキレイに洗い、自然乾燥させる。
③②の梅→氷砂糖→梅→氷砂糖→梅→…の順に容器に入れる。
④未練を残さず、豪快に焼酎を注ぎ入れる。
⑤「ちょっと味見…」などとチョッカイを出さず、2年経つまで冷暗所で保存する。
※糖分が均等になるように、時々ビンを揺り動かして「美味しくなぁ~れぇ~」と唱える
スーパーで青梅を見かけたら、みなさんも是非、お試しあれ。
2年後に開けるタイムカプセル

勘の良い方は、お判りですよね。
そう、
酒の仕込み。

今の季節、地元和歌山のスーパーや道の駅には、梅、梅、梅、と梅が溢れています。
日本一の生産量を誇る和歌山県みなべ町の南高梅が、5月末に発生した台風によって多数落下。
なんとか枝にしがみついて耐えた梅にも、折れた枝で擦り傷のような跡がつき、大幅な出荷減。
と言われている中、地元スーパーには梅がいっぱい。

しかも激安、1㌔298円。



ところで、梅酒づくりに溶けにくい氷砂糖をなぜ使うか知っていますか?
顆粒の砂糖を使えば、あっちゅう間に溶けるのに…。
氷砂糖でなければ駄目な理由があるんですよ、これがまた。
これは、「溶けにくい」という性質を利用して、
梅のエキスや香りを引き出すためなんです。
梅酒づくりのポイントは、2度の浸透圧を利用するということ。
一般的に、梅酒を作る時に使うのは、

青梅、焼酎(ホワイトリカー)、氷砂糖 の3つ。
これを役割分担させてみると、
・エキスや香りの元:梅
・浸透圧を使って梅のエキスを引き出すもの:焼酎と氷砂糖
となります。
梅のエキスや香りなどは、梅の実の中にありますが、
これが出てくるきっかけの第1段階が、アルコール分子と水分(焼酎)。
梅の実の中にある糖分が、実の外と同じ糖度にしようとして、
実の外にあるアルコールと水分子を実の中に引っ張ります。
梅の実から、糖分が外に出れば良いのでは?と思いますが、
梅の表面にあいている小さな穴は、アルコールや水のように
小さい分子を通す事が出来ても、糖分を通す事は出来ません。
そのため、実の外にあるアルコールや水の分子を、実の中に引っ張ります。
その結果、元々の梅の実よりも、膨らみます。



そして、アルコールと仲が良い芳香成分などのエキスが、
梅の実の中に入ってきたアルコールに溶け出します。
これが最初に起こる浸透圧の働き。
※この梅の実が膨らんだ状態は、梅の実が酔っぱらった状態

そして、次にはたらくのが氷砂糖。

氷砂糖は、その特性から、じわじわと焼酎の中に溶けて行きます。
氷砂糖がじわじわ溶ける事で、梅の実の外では少しずつ糖度が上がっていきます。
最初の浸透圧では、梅の実の外よりも梅の実の中の糖度が高いため、
アルコールや水分が梅の実の中に入って行きましたが、今度はその逆が起こります。
梅の実の糖度よりも梅の外の糖度が上回ると、今までの圧力バランスが崩れ、
今度は梅の実の中に入っていたアルコールやエキスなどが外に引っ張り出されます。
その結果、梅がしぼみ始めます。

これが第2段階の浸透圧。
ゆっくりと時間をかけてこの反応を起こすことで、コクのある美味しい梅酒ができるんです。
これらの反応が落ち着くまでには、半年から1年。
糖度が低い場合には、第2段階の浸透圧が低いため、さらに時間がかかります。
甘~いお酒が苦手なyo!が作る梅酒は、糖度が低め。
そのため、梅のエキスがでて、まろやかになるまで2年以上かかります。
だから、いつも多めに(4㍑)作ります。


【yo!特製梅酒の作り方】~甘さひかえめ~
・青梅 1kg
・氷砂糖 330g
・焼酎 2L
①青梅を1時間ほど水にさらして灰汁をぬく。
②青梅のヘタを取ってキレイに洗い、自然乾燥させる。
③②の梅→氷砂糖→梅→氷砂糖→梅→…の順に容器に入れる。
④未練を残さず、豪快に焼酎を注ぎ入れる。
⑤「ちょっと味見…」などとチョッカイを出さず、2年経つまで冷暗所で保存する。
※糖分が均等になるように、時々ビンを揺り動かして「美味しくなぁ~れぇ~」と唱える

スーパーで青梅を見かけたら、みなさんも是非、お試しあれ。

Posted by yo! at 14:55│Comments(0)
│ごちそうマンマ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。